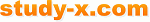www.さとなお.com(さなメモ): 人に仕事を合わせるという記事を読んで、中学生を指導するものとして、どんな立場をとっていくべきか考えさせられました。
さとなおさんが言うとおり、高度経済成長期の日本は「仕事に人を合わせる」という考えが当たり前でした。ある仕事があって、その仕事を速く、効率よく出来ることがよいという考え。誰もが、ひとつの仕事を効率よく出来るように訓練されます。
教育でいうところの「あなたは数学が得意だから、数学は勉強しなくて良い。そのかわり英語が弱いから、英語が平均点になるように頑張ろうね」と指導すること。この考え方とつながっているでしょう。
しかし、これからは「人に仕事を合わせる」という考えになる。人間一人一人の特性を生かした仕事に就けるようにしようと。
教育では「あなたは数学が得意だから、数学をもっと伸ばしましょう。」と指導すること。
日本が高度経済成長を遂げたのは「仕事に人を合わせる」という考え方のおかげでした。しかし、豊かになった日本は「豊かさだけが本当の幸せではない」と気がついてしまった。自分の能力を発揮して社会の役に立つ、というところに本当の幸せがある。
そういう考え方の延長上に、「人に仕事を合わせる」というのがあるのでしょうね。
13歳のハローワークという本は、中学生だけではなく中高年にも売れたそうです。30代、40代、50代の大人たちがそういう価値観に飢えていたからではないでしょうか。
塾としては、どちらで指導していけばよいのか非常に悩むところです。
今のところ、わたしの塾は「どっちつかず」。
生徒の性格を考慮して、考え方を使い分けている、といったところでしょうか。
◆登録カテゴリ
4000教育